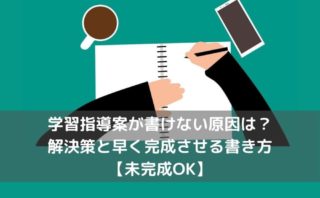教材研究ノートの作り方ってあるのかな?
子どもたちのためにもなる教材研究のハウツーを知りたい!
こんな悩みを解消します。
教材研究はぜひ手書きで、ノートに作ることをオススメします。
なぜなら、ノートで行うことで3つのメリットが得られ、しかも良い授業が作れるから。
- 教材研究をノートで作る3つのメリット
- 僕が実践している教材研究ノートの書き方
- 教材研究をスピードアップさせる3つのポイント
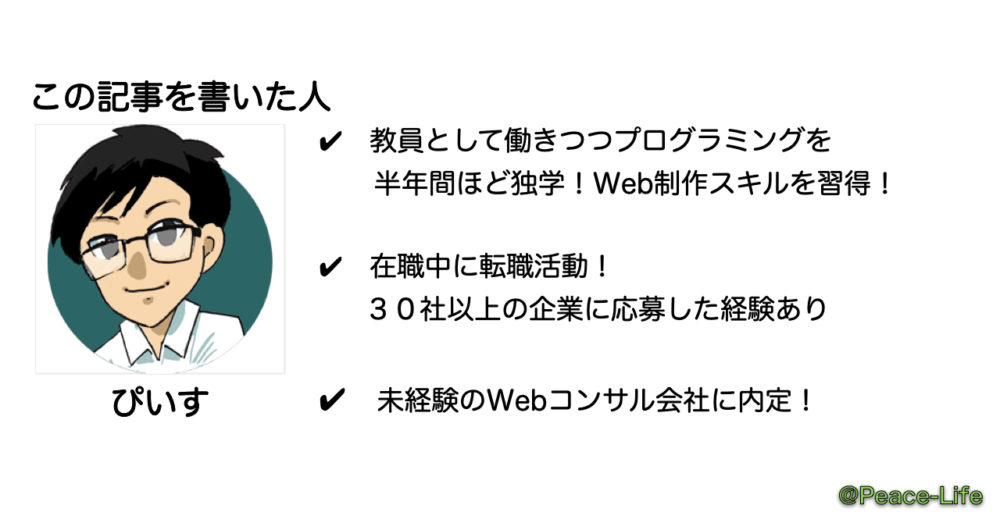
記事を書いている僕は現職の中学校教員。
- およそ半年間でプログラミング独学
- 3ヶ月の転職活動で未経験のWEBコンサルタント会社から内定
- 「教員の働き方コンサルタント」として情報発信中
おかげさまでブログは15万PVを突破。
Twitterでは6,000人のフォロワーさんとつながることができました!
この記事では僕が小学校、中学校と10年間の経験から得た教材研究の方法をまとめました。
これから紹介する方法を実践したことで
- 授業研究の効率アップ
- よりレベルの高い授業の実践
- 学級経営の安定

授業で悩むことも減り、ゆとりある生活を送れるようになりました!
この記事では教材研究をノートで行うことで得られる3つのメリット、そして実際の使い方やポイントを解説します。
記事を読み終えれば、明日からあなたの教材研究はさらにレベルが上がります。

スピードも上がり、より定時で帰れるようになりますよ。
教材研究ノートを作って得られる3つのメリット


どうして教材研究をノートにするといいの?

ノートに書くと3つのメリットがあるからです!
教材研究ノートを作って得られる3つのメリットは次の3つです。
- アイデアが出やすい
- 安心感をもてる
- 保管して使い回せる
アイデアが出やすい
 教材研究をノートで書くことで得られる1つめのメリットは「アイデアが出やすい」ことです。
教材研究をノートで書くことで得られる1つめのメリットは「アイデアが出やすい」ことです。
なぜなら、自由に手を動かして書くことができるから。
しかし、アイデアを出すときには圧倒的に手書きがいいです。
手書きであれば直感的に書くことができますよね。
- 文字
- 図
- イラスト
- 表

僕も頭で思いついたアイデアはすぐにメモをします。
後で見返したとき、メモからさらに気づきが発生して授業のアイデアがふくらむことがあります。
単語だけ、発問だけでもOK!

まずは思いつくまま、手書きでアイデアを書き出してみましょう。
最後にアイデア同士をつなげていくことで、よりよい授業が作れるようになります。
安心感をもてる
教材研究をノートに作る2つめのメリットは「授業において安心感が得られる」こと。
なぜなら、困ったときにもノートを見ることでコンパスとなるからです。
その時間ごとに子どもたちに身につけてほしい力があり、そのために授業の流れを考えますよね。

しかし、授業は必ずしも思い通りにいくとは限りません。
- 子どもが突然、体調を崩してしまった
- 授業で想定していなかった意見が出された
- 健康診断などで中断された

そんな突発的なことがあっても、ノートがあれば大丈夫。
見直せば、どこから授業を再開すればよいのかすぐに分かります。
ブレることなく、安心して授業ができるようになります。
保管して使い回せる

教材研究をノートに作る3つめのメリットは「保管して使い回せる」こと。
これにより、仕事のスピードが早くなります。
- 1年分の教材研究ノートを保管しておく
- 再度、同じ学年を担当する
- 見直して授業することで研究時間を短くできる
もちろん、学習指導要領が変わることで教科書の内容も変わることはあります。

それでも指導内容がまるっと変わってしまうことは起きないはず。
なにより、一回の授業のためにしっかり研究をしたノートであれば、大きく修正をする必要はありません。
大きな役割を担うことになる前に、教材研究の貯金をしておくことをおすすめします。

貯金はやがて、あなたを「定時で帰る」という資産につなげてくれますよ。
>>すぐ実践!仕事が早い先生になるための3つの習慣術【明日からできます】
教材研究ノートの作り方は見開き1ページで1時間


教材研究ノートってどうやって作るといいの?

1時間を見開き1ページで作りましょう!
ノートは見開きで1ページを1時間の研究で使うことをおすすめします。
なぜなら、脳の機能をフル活用できるから。
- 左脳:論理的な思考
- 右脳:空間的な認知

左右にある脳の機能に合わせて書く方法があるんです。
左側は授業の流れを書く
見開きの左1ページには授業の流れを書きましょう。
なぜなら、左脳を有効活用できるから。
授業における流れを論理的に考え、その時間の「めあて」までの流れを整理することは左脳で行うことが効果的。
- 導入
- 展開
- まとめ

左脳に近い「左側」のページに流れを書くことを意識しましょう。
右側は板書や資料を書く
見開きの右1ページには「板書」や「使う資料」を想像して書くことがおすすめ。
なぜなら、右脳を有効活用できるから。
子どもたちの発言などを想像し、黒板をイメージして書くことに適しているんですよね。

脳機能を使って合理的に教材研究をすることで、よりよい授業が考え出されますよ!
- 教材研究ノートは見開き1ページで1時間分
- 左ページは「授業の流れ」を書こう
- 右ページは「板書」や「資料」などを書こう
教材研究がスピードアップする3つのポイント


教材研究ノートの作り方はわかったけど、少しでも早く作るポイントってあるのかな?

次の3つを意識してみましょう!
- 完璧ではなく「8割」を目指す
- 授業の流れは「展開」から
- 小学校ならまず1教科だけ
完璧ではなく「8割」を目指す
教材研究は完璧なプランではなく「8割」を目指しましょう。
なぜなら、残り「2割」は子どもたちの発言、行動で変化するからです。

しかし、それと同時に子どもたちの姿も大切にしなければいけません。
- 子どもたちの発言
- 子どもたちの活動
- 子どもたちの変容
これらがあることで、授業が完成すると思いましょう。
筋金入りでガチガチなプランは、柔軟性に欠けます。
若い先生ほど「授業案の流れ通りにしないとダメだ!」という先入観を持ってしまい、目の前の子どもたちが見えていないこともあります。

「8割」で作り、残りは子どもたちの姿で作るような感覚でOK!
>>子どもが話を聞くようになる!学級経営がうまくいく先生の会話術とは?【ヒント:5W1H】
授業の流れは「展開」から
授業の流れは「展開」から書きましょう。
なぜなら、「展開」に最も子どもたちに身に着けてほしい学習課題が設定されるからです。

僕も最初は「導入」から順番に考えていました…
たしかに、授業の「つかみ」は大切です。
しかし、それは「展開」につなげるためのもの。
- 展開
- 導入
- まとめ
指導案を早く書く方法については別の記事でも解説しています。

いつも早く書けなくて困ってる!という人は参考にしてください。
小学校ならまず1教科だけ
小学校の先生は、まず1つの教科だけこの方法で教材研究をしましょう。
なぜなら、小学校では多くの教科を教える必要があり準備する時間をかけすぎると辛くなるからです。
僕も経験したことがありますが、小学校の教員はともかく研究量が多すぎます。
- 国語
- 算数
- 体育
- 社会
- 理科
- 家庭科
- プログラミング
- 道徳
- 英語

小学校の先生は仕事量がすごいことになっているのではないでしょうか。
まずは「国語」か「算数」だけでも良いと思います。
あとは他の教科でも同じように研究をすればよいだけ。
上手に時間を使って、教材研究に取り組みましょう。
その時間術はあなたの「強み」としても発揮されます。
>>どんな企業にも通用する!教員からの転職で活かせる5つの強みとは
まとめ
改めてこの記事のまとめです。
- アイデアが出やすい
- 安心感がある
- 保管して使い回せる
- 見開き1ページを使う
- 左ページ:左脳の機能として授業の流れ
- 右ページ:右脳の機能として黒板のイメージ
- 完璧ではなく「8割」を目指す
- 授業の流れは「展開」から作成する
- 小学校ならまず1教科だけ実践する
教材研究は教師の最も重要な仕事です。こだわれば時間をかけることもできます。
より効果的かつ、効率的に行うべきです。
授業がうまくなれば、学級経営も安定します。

結果、心にゆとりがうまれるので、子どもたちと楽しい毎日を過ごせます。
良いループが完成するはず。
ぜひ、ノートによる教材研究に取り組んでみてください。
今回は以上です。
YouTubeもはじめました!
人気記事 教員に強い転職エージェント3選!登録するならコレだけでOKです【最新版】
人気記事 教員でも簡単!10分で完成!WordPressブログの始め方完全解説【クイックスタート】
このブログでは
- 学級経営がうまくいかず困っている先生
- 仕事を効率的に進めて早く帰りたい先生
- 仕事がつらくて転職しようか悩んでいる先生
こんな先生に向けて役立つ情報を発信しています。

Twitterでも日頃、情報を発信しています!
ぴいすへの質問は下記のお問い合わせフォームからお気軽にどうぞ!